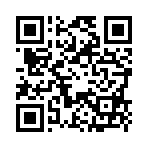スポンサーサイト
上記の広告は2週間以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書くことで広告が消せます。
カーペットしみとり
カーペットの染み取りに
挑戦します《基本編》
カーペットの染み取りに挑戦です。
ビルクリーニング技能士の基本技術。
大雑把に紹介します。
なんの汚れかもさっぱりわからない、という前提です。
最大のポイントは、ゴシゴシこすって汚れを広げないことです!!
①水性の汚れか油性の汚れかを見極める。
固めに絞った濡れタオルを人差し指を覆い、
汚れを広げないように、汚れの外ふちから中心に向かってこすります。
タオルが汚れていれば水性の汚れ、帰ってこなかったら油性の汚れです(シンプル!)。
②まず水性の汚れ。①の要領で、汚れが戻ってこなくなるまで水だけで除去します。
汚れがタオルに戻らなくなったら、中性洗剤をあまり広範囲に広げないよう、汚れにスプレーします。
台所洗剤を10倍くらいに薄めたものでいいと思います。
③上に乾いたタオル(もしくはキッチンペーパー)をしいて、ブラシで押さえ、振動。
タオルに汚れを移しま~す。
ゴシゴシこすると汚れを広げてしまうので、ブラシの位置は固定したまま。
④向きを変えて、
⑤これを何度か繰り返します。せっかくタオルに移した汚れを戻さないようにタオルの位置をこまめに変えながら。
⑥汚れがあらかた取れたら清水でリンスします。
汚れよりひとまわり広範囲に水をシャッとスプレーして、③の要領でタオルに水分を移します。
⑦終了~。毛並みをそろえてください。
次、油性汚れ。水拭きのタオルでは反応がなかったほうです。
⑧専用の油性汚れ用染みとり剤(溶剤系)があればいいですけど、手に入りやすいのは除光液やベンジン。
⑨綿棒で塗布してやると、すぐに汚れが移ってくるのが油性汚れの証拠です。
⑩水性汚れと同じように、溶剤を塗った箇所に乾いたタオル等をかぶせ、汚れを移します。
⑪汚れが戻ってこなくなったら、仕上げに②~⑥の作業をしてください。
⑫完成~。
| 建物・生活環境の洗浄士 にもっと聞きたい! | 建物・生活環境の洗浄士 をもっと知りたい! | 建物・生活環境の洗浄士 にキレイを頼みたい! |
タグ :建物・生活環境の洗浄士
床にワックスを塗る注意点
床ワックス塗装に
挑戦します!
床にワックスを塗ることは、単にピカピカの美観を維持する目的以外に、
・建物の床材に傷がつかないようにする、
・ツルツルの床をさーっと掃き拭きできるので、日常の清掃が楽になる、
という目的があって、建物の維持管理上、欠かせないものです。
ホームセンターに行けば、容易に手に入れることができるので、自分でやってみる、という方も多いようです。
最低限の注意点を挙げてみます。
①晴れて暖かい日に作業すること。
床用ワックスは、有効成分が水に溶かしてあり、塗りやすくなっている製品です。
天気が悪く湿度の高い日は乾燥が悪く、仕上がりも良くありません。
(あまり暑くてカンカン照りの日も乾燥が速すぎるので、作業が難しいです!)
また、気温が5℃より低いような寒い日は、ワックスがうまく固まらず、粉がふいたような状態になり、失敗します。
そもそも、お掃除ですから、天気のいい日に、パーっと窓を開けて、気持ちよくしたいですよね。
②ワックスを塗る前に、下地の汚れをしっかり洗浄して落とすこと。
「ワックス」は、和訳すると「ろう」ですが、現在主流で使われている「ワックス」は「ろう」ではありません。
アクリルやウレタンといった、石油を原料にした樹脂の膜。
単純な話、汚れの上から膜を張ってしまったら、その汚れはずっと取れません!
膜を張る前にできるだけ丁寧に汚れを取り除き、その上にコーティングしてあげるのです。
材質によって洗浄方法が違いますが(フローリング)、
ビニル製の床だったらアルカリ性の洗剤でOKなので、ジャブジャブ洗えます。
ただし洗浄の際に使った洗剤成分や水分が残っていたら、うまくワックスが塗れませんので注意。
③道具の問題。
最近では柄のついたパット器具が市販されているので、それが便利かと思います。
もちろん濡れタオルとかスポンジでも塗れるんですが。
角張ったものの方がキッチリ仕上がると思います。
④後々のメンテナンスを考えてワックスを塗ること。
ワックスには塗りっぱなしにはできない、という欠点があります。
だんだんツヤがなくなってきたら数ヶ月ごとに塗り足してやればいいです。
ただし塗りすぎないこと。
塗り足しの場合は隅々まで塗らないこと。
人通りがあって削れている部分と、隅っこのほうのまだツヤのある部分。
同じだけワックスを塗る必要は全然ないです。
それから、塗装前の洗浄をどんなに丁寧にしても、
汚れがほんの少しずつでも残っていたら(目に見えない程度に残っている)黒ずみになります。
また、塗ってから時間が経過したワックスは、黄変という現象で、茶色っぽくなってきます。
キレイな床面をキープするには、
ワックスをハクリして、また新しく一からのワックスを塗る必要がでてきます。
この「ハクリ」は一般の方ではかなり大変な作業。
必要以上にワックスを塗りこめてしまうと、「ハクリ」がさらに手強くなってしまいます。
フローリングにワックスをかける
| 建物・生活環境の洗浄士 にもっと聞きたい! | 建物・生活環境の洗浄士 をもっと知りたい! | 建物・生活環境の洗浄士 にキレイを頼みたい! |
タグ :建物・生活環境の洗浄士
掃除機のかけ方のコツ
部屋のスミズミまで
掃除機をかけます。
どこの家にも、室内には必ずダニがいます。そして必ず目に見えない微粒子、ハウスダストが舞っています。
いずれも頭の痛いアレルゲン物質。
対策は、とにかくマメな掃除機かけが一番、と言われています。
掃除機かけをしましょう!
掃除機かけのポイントは①前進作業を心がけること。②隙間のない直線作業をすること。この2点です。
①掃除機のコンセントは自分(掃除機)の進行方向よりも後ろからとってください。
掃除機の電源コードが邪魔で掃除機がかけにくい、なんて、冗談みたいです。
必要な場合には面倒くさがらず(!)コンセントの差し替えにいってください。
②よく見かけるんですが、自分を中心に放射状に、扇形に掃除機をかけている奥さん。それはダメです。
端から端に、隙間のできないよう几帳面にこなしていく。
部屋の端から、吸い込みノズルを、自分の腕の伸縮の範囲で前後に一往復。
ノズル幅が少し重なるくらい横にずれて、一往復。
さらに横にずれて一往復・・・・。
目に見える大きなゴミの散らかっている箇所だけではいけません。
ゴミの見えない箇所にも必ずノズルを当ててください。
掃除機かけの終わった箇所の長方形が、次第に広がっていくようなイメージで。
通常の家庭用の掃除機(200W以上)であれば、フローリングやシート張りの床の場合、ざっとで十分です。
これが、特にカーペットや畳の部屋で、アレルゲンを除去をするつもりで作業を行うなら、
畳1畳に30秒から1分くらいかけるつもりで、ゆ~っくり仕上げます。
畳は目に沿ってかけてくださいね。
| 建物・生活環境の洗浄士 にもっと聞きたい! | 建物・生活環境の洗浄士 をもっと知りたい! | 建物・生活環境の洗浄士 にキレイを頼みたい! |
タグ :建物・生活環境の洗浄士
カテゴリ
ブログ内検索
プロフィール
日本洗浄士協会
QRコード